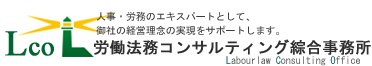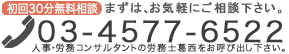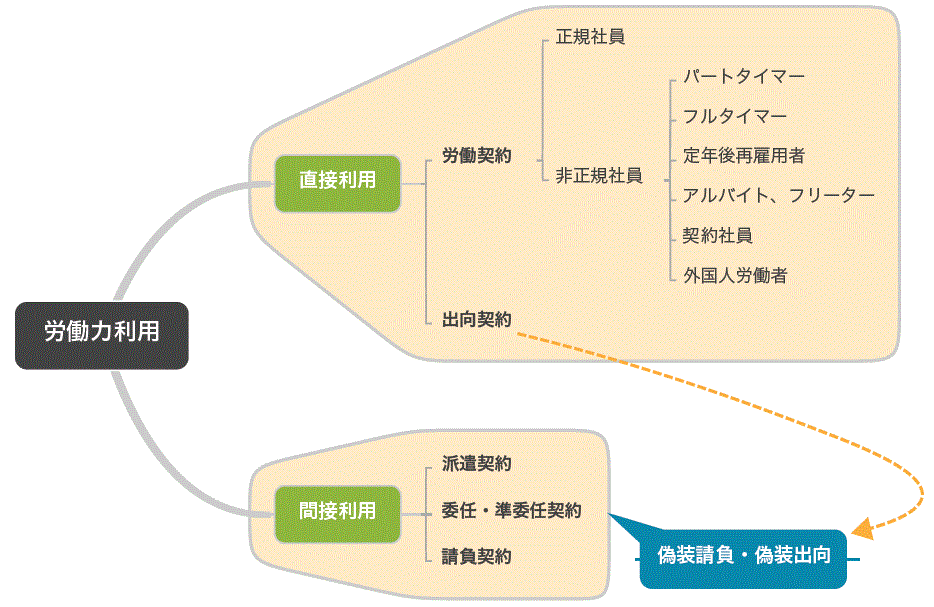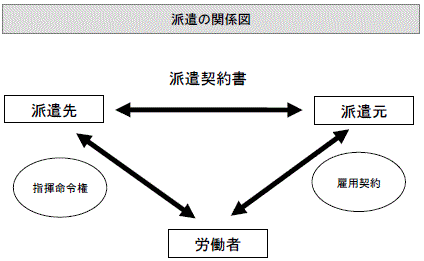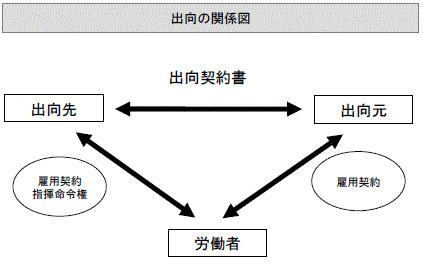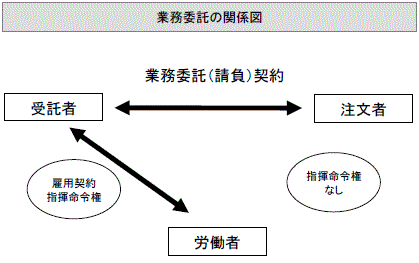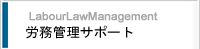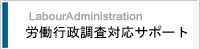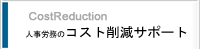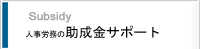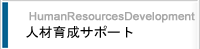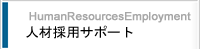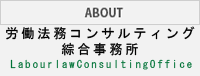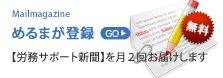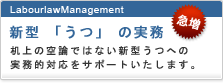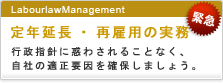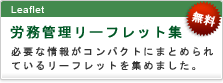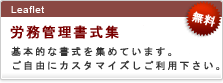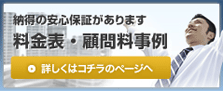‚±‚ê‚ç‚ج”ٌگ³‹KŒظ—p‚ح”ل”»‚³‚ê‚邱‚ئ‚حڈ‚ب‚‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAژہچغ‚ة‚حکJ“ژزگ”‚ھ‹}‘‚µ‚ؤ‚¨‚èپAٹé‹ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح“Kگط‚بکJ–±ٹا—‚ًچs‚ء‚ؤپAٹˆ—p‚·‚邱‚ئ‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚ـ‚·پB‚»‚ج‚½‚ك‚ة‚àپAٹضکA‚·‚é–@—¥‚ًگ³‚µ‚—‰ً‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA‚ئ‚±‚ةƒٹƒXƒN‚ھ‚ ‚é‚©‚ً’m‚ء‚ؤپAƒٹƒXƒNƒ}ƒlƒWƒپƒ“ƒg‚جژ‹“_‚©‚ç‘خ‰‚·‚邱‚ئ‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB
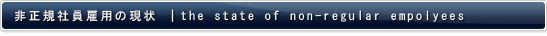
 |
کJ“—ح’²چ¸پi2011”N•½‹دپj‚©‚ç”ٌگ³‹KژذˆُŒظ—p‚جŒ»ڈَ‚ًٹm”F‚·‚é |
| ‹ك”N‚إ‚حپAٹé‹ئ‚ة‚¨‚¯‚éگlچق—ک—p‚ھ‘½—l‰»‚µپA”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ئ‚µ‚ؤ‹N‹ئ‚ةŒظ—p‚³‚ê‚éکJ“ژز‚جٹ„چ‡‚ھچ‚‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAژہچغ‚ة‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚بŒظ—pŒ`‘ش‚جکJ“ژز‚ھ‚ا‚ج’ِ“x‚جٹ„چ‡‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پA‘چ–±ڈب“Œv‹ا‚جپuکJ“—ح’²چ¸پvپi•½گ¬23”N•½‹دپj‚ً‚ف‚ؤٹm”F‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB •½گ¬23”N•½‹د‚جŒظ—pژزپi–ًˆُ‚ًڈœ‚پj‚ح4918–œگl‚ئ‚ب‚èپA‘O”N‚ة”ن‚×25–œگl‚ج‘‰ء‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج‚¤‚؟پAگ³‹K‚جگEˆُپEڈ]‹ئˆُ‚ح3185–œگl‚ئ25–œگl‚جŒ¸ڈ‚ئ‚ب‚ء‚½پBˆê•ûپAƒpپ[ƒgپEƒAƒ‹ƒoƒCƒgپA”hŒژذˆُپAŒ_–ٌژذˆُ‚ب‚ا‚ج”ٌگ³‹K‚جگEˆُپEڈ]‹ئˆُ‚ح1733–œگl‚ئ48–œگl‚ج‘‰ء‚ئ‚ب‚ء‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ’jڈ—•ت‚ة‚ف‚é‚ئپA’jگ«‚حگ³‹K‚جگEˆُپEڈ]‹ئˆُ‚ھ2200–œگl‚ئ‚ب‚èپA13–œگl‚جŒ¸ڈ‚ئ‚ب‚éˆê•ûپA”ٌگ³‹K‚جگEˆُپEڈ]‹ئˆُ‚ح545–œگl‚ئ31–œگl‚ج‘‰ء‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBڈ—گ«‚حپAگ³‹K‚جگEˆُپEڈ]‹ئˆُ‚ھ985–œگl‚ئ‚ب‚èپA12–œگl‚جŒ¸ڈ‚ئ‚ب‚éˆê•ûپA”ٌگ³‹K‚جگEˆُپEڈ]‹ئˆُ‚ح1188–œگl‚ئ18–œگl‚ج‘‰ء‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB Œظ—pژزپi–ًˆُ‚ًڈœ‚پj‚ةگè‚ك‚é”ٌگ³‹K‚جگEˆُپEڈ]‹ئˆُ‚جٹ„چ‡‚حپA•½گ¬23”N•½‹د‚إ35.2پ“‚ئ‚ب‚èپA‘O”N‚ة”ن‚×0.8ƒ|ƒCƒ“ƒg‚جڈمڈ¸‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA’jڈ—•ت‚ة‚ف‚é‚ئپA’jگ«‚ح19.9پ“‚ئ1.1ƒ|ƒCƒ“ƒg‚جڈمڈ¸پAڈ—گ«‚ح54.7پ“‚ئ0.7ƒ|ƒCƒ“ƒg‚جڈمڈ¸‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚ب‚¨پAپuکJ“—ح’²چ¸پv‚إ‚حپA‹خ‚كگو‚جŒؤڈج‚ة‚و‚ء‚ؤŒظ—pŒ`‘ش‚ھ‹و•ھ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚إ‚·‚ج‚إپA‚½‚ئ‚¦‚خŒ_–ٌژذˆُ‚âڈْ‘ُژذˆُ‚ھژہ‘ش‚ئ‚µ‚ؤ‚ا‚ج‚و‚¤‚ب“‚«•û‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éکJ“ژز‚ب‚ج‚©‚حپA–¾ٹm‚ة‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚½‚¾‚µپAŒ_–ٌژذˆُ‚âڈْ‘ُژذˆُ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پ[‚ئ‚ج‘خ”ن‚إپAگ³ژذˆُ‚ئ‚ظ‚ع“¯‚¶ڈٹ’èکJ“ژٹش‚ً“‚کJ“ژز‚ھ‘½‚¢‚à‚ج‚ئ‘z’肳‚ê‚ـ‚·پB |
|
 |
”ٌگ³‹Kژذˆُ‘‰ء‚جŒ´ˆِ |
| پuکJ“—ح’²چ¸پv‚ة‚¨‚¯‚éŒظ—pŒ`‘ش•تŒظ—pژزگ”‚جگ„ˆع‚©‚çپA‚»‚ꂼ‚ê‚جژ‘م‚ة‚¨‚¢‚ؤ”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ھ‘‰ء‚µ‚½Œ´ˆِ‚ً•ھگح‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئپA•½گ¬ˆêŒ…‘م‚ـ‚إ‚حپAگ³ژذˆُ‚ًٹـ‚ك‚ؤ‘S‘ج‚جŒظ—pژز‚ھ‘‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚’†‚إپA‰ئ’ëگ¶ٹˆ‚ب‚ا‚جژ–ڈî‚ة‚و‚èڈ]—ˆڈAکJ‚µ‚ة‚‚”ƒ‚ء‚½‘w‚ھپA’Zژٹش‚جƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پ[‚ب‚ا‚ئ‚µ‚ؤڈAکJ‚ج‹@‰ï‚ً“¾‚邱‚ئ‚إپAƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پ[‚âƒAƒ‹ƒoƒCƒg‚ً’†گS‚ئ‚µ‚½”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج‘‰ء‚ھŒ©‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پB ˆê•ûپA•½گ¬“ٌŒ…‘م‚حپAگ³ژذˆُŒظ—p‚ھ—}گ§‚³‚ê‚é’†‚إپAگ³ژذˆُ‚ئ‚ظ‚ع“¯‚¶کJ“ژٹش‚ً“‚ƒtƒ‹ƒ^ƒCƒ€‚جٹْٹشŒظ—pژز‚â”hŒژذˆُ‚ً’†گS‚ة”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ھ‘‰ء‚µ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB‚آ‚ـ‚èپAڈ]—ˆ‚جگ³ژذˆُ‚ج—vˆُ•s‘«‚ً•â‚¤‚ئ‚¢‚¤”ٌگ³‹Kژذˆُ—ک—p‚©‚çپAگ³ژذˆُ‚ج‘م‘ض‚ئ‚µ‚ؤ”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ً—ک—p‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ةپA‚»‚ج—ک—p–ع“Iژ©‘ج‚ة•د‰»‚ھ‚ف‚ç‚ê‚ـ‚·پB ‚±‚¤‚µ‚½”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج‘‰ء‚حپAƒ}پ[ƒPƒbƒg‚ھƒOƒچپ[ƒoƒ‹‰»‚µپAچ‘چغ“I‚ب‰؟ٹi‹£‘ˆ‚ة‚³‚炳‚ê‚éٹé‹ئ‚ة‚¨‚¢‚ؤپAگ³ژذˆُŒظ—p‚إچ‚ٹz‰»‚µ‚½گlŒڈ”ï‚ً—}‚¦‚é•K—v‚ة”—‚ç‚ꂽŒ‹‰ت‚ئ‚à‚¢‚¦‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAڈ¤•iƒ‰ƒCƒtƒTƒCƒNƒ‹‚ھ’Z–½‰»‚µ‚½‚±‚ئ‚ة”؛‚¢پAŒإ’è”ï‚ئ‚ب‚éگ³ژذˆُŒظ—p‚جˆغژ‚ھ“‚‚ب‚èپA‚±‚ê‚ً—¬“®”‚·‚邽‚ك‚ة”ٌگ³‹Kژذˆُ—ک—p‚ًٹˆگ«‰»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚é–ت‚à‚ ‚é‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB |
|
 |
”ٌگ³‹KژذˆُŒظ—p‚جژہ–±“I–â‘è“_ |
| ڈم‹L‚ج‚و‚¤‚بƒ}پ[ƒPƒbƒgڈَ‹µ‚ج‚à‚ئٹé‹ئ‚ھگ¶‚«ژc‚é‚ة‚حپA”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ئ‚µ‚ؤ’Zٹْٹش‚جٹْٹشŒظ—pŒ_–ٌ‚ً’÷Œ‹‚µ‚ؤپA‚»‚جکJ“—ح‚ً—ک—p‚·‚éˆبٹO‚ة‚ح“r‚ح‚ب‚پA‚»‚ج‘‰ء‚ح•K‘R‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB ‚»‚±‚إ–â‘è‚ئ‚ب‚é‚ج‚حپA‚»‚جڈ]‹ئˆُ‚ئ‚جگM—ٹٹضŒW‚ً‚¢‚©‚ةڈّگ¬‚·‚é‚©‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB’·ٹْŒظ—p‚إ‚حپA‚»‚جŒظ—p•غڈل‚ج‰؛‚إ‚جگlٹشٹضŒW‚àٹـ‚ك‚½گlٹشٹضŒW‚ًٹـ‚ك‚½گM—ٹٹضŒW‚جچ\’z‚ًچl‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·‚ھپAٹْٹشŒظ—p‚إ‚ح‚»‚ê‚à–]‚ك‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ئ‚جگM—ٹٹضŒW‚جچ\’z‚حپAŒ_–ٌ‚إ–ٌ‘©‚µ‚½“à—e‚حژç‚é‚ئ‚¢‚¤ژpگ¨‚ة‹پ‚ك‚´‚é‚ً“¾‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB |
|
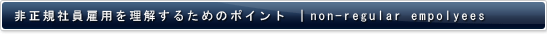

 |
گ³‹Kژذˆُ‚ئ”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج‘ٹˆل“_ |
| گ³‹Kژذˆُ‚ئ”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ئ‚ج‘ٹˆل“_‚حپAٹب’P‚ةŒ¾‚¤‚ئپA‘Oڈq‚جگ³‹Kژذˆُ‚ج“ء’¥‚ھ”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ة‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB | |
 |
”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج“ء’¥‡@پ@چج—p‹Kگ§پy“üŒûک_پz |
| Œْگ¶کJ“ڈب‚جژگ–â‹@ٹض‚إ‚ ‚éکJ“گچôگR‹c‰ïکJ“ڈًŒڈ•ھ‰ب‰ï‚إ‚حپAکJ“Œ_–ٌ‚ح–³ٹْŒ_–ٌ‚ھŒ´‘¥‚إ‚ ‚èپA—LٹْکJ“Œ_–ٌ‚حپAپu—صژپEˆêژ“I‚ب‹ئ–±پv‚ةŒہ’è‚·‚é’÷Œ‹ژ–—R‹Kگ§پi“üŒû‹Kگ§پj‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ً’†گS‚ئ‚·‚éکJ“ژز•غŒى‚ج‚½‚ك‚ج‹Kگ§‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹cک_‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA2012”N3Œژ16“ْ‚جپuکJ“Œ_–ٌ–@‚جˆê•”‚ً‰üگ³‚·‚é–@—¥ˆؤ—vچjپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج“ڑگ\‚إ‚حپA“üŒû‹Kگ§‚حڈœٹO‚³‚êکJ“Œ_–ٌ–@‚ة‚ح“üŒû‹Kگ§‚ح‹K’肳‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپBٹé‹ئ‚ج”ٌگ³‹Kژذˆُ‚جچج—p‚ة‚ح‰½‚ç‹Kگ§‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB ‚ـ‚½پA”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ح—LٹْŒظ—pŒ_–ٌ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ‘½‚پAٹْٹش–—¹‚ة‚و‚èکJ“Œ_–ٌ‚ح‰ًڈء‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚ً‘O’ٌ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚邽‚كپAچج—pژ葱‚«‚àپA•M‹LژژŒ±‚ھ‚ب‚©‚ء‚½‚èپA–تگع‰ٌگ”‚à1‰ٌ‚إچد‚ٌ‚¾‚èپAŒˆچد‚à“X’·‚â•”‰غ’·Œˆچد‚إچد‚ٌ‚¾‚è‚·‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB پ¦گ³ژذˆُ‚ئ‚جچج—pژ葱‚«‚ج‘ٹˆل‚à“¯ˆêکJ““¯ˆê’ہ‹à‚ً”غ’è‚·‚éˆê‚آ‚ج—v‘f‚ئ‚ب‚肦‚ـ‚·پB |
|
 |
”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج“ء’¥‡Aپ@گ³ژذˆُ‚ئ‚ج“¯ˆêکJ““¯ˆê’ہ‹àک_پy“üŒûک_پz |
| –¯–@ڈمپAŒ_–ٌ“à—e‚ح“–ژ–ژزٹش‚إژ©—R‚ةŒˆ’è‚إ‚«‚邱‚ئ‚ھŒ´‘¥‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپAکJ“–@‚حکJ“ژز•غŒى‚جٹد“_‚©‚çپAکJ“ڈًŒڈ‚ج“à—e‚ً‹K—¥‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ê‚ة”½‚µ‚ب‚¢Œہ‚è‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAکJ“ڈًŒڈ‚à“–ژYگ·‚ٌ‚إژ©—R‚ةŒˆ’è‚إ‚«‚é‚ج‚ھŒ´‘¥‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‚آ‚ـ‚èپAگ³ژذˆُ‚ئ”ٌگ³‹KژذˆُپA‚±‚ئ‚ب‚éŒظ—pŒ`‘ش‚ة‰‚¶‚ؤپAˆظ‚ب‚é’ہ‹à‚ًگف’è‚·‚邱‚ئ‚حپAŒ_–ٌژ©—R‚جگ¢ٹE‚ة‚ ‚é‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB ƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ€کJ“–@‘و‚Wڈً‚إ‚حپAˆê’è—vŒڈ‚ً–‚½‚µ‚½ƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پ[‚ة‚آ‚¢‚ؤپA’ZژٹشکJ“‚ئ‚¢‚¤Œظ—pŒ`‘ش‚¾‚¯‚ً——R‚ةکJ“ڈًŒڈ‚ة‚آ‚¢‚ؤچ·•ت“Iژوˆµ‚¢‚·‚邱‚ئ‚ھ‹ضژ~‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‘Oڈq‚ج”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج“ء’¥‡@‚âŒمڈq‚ج”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج“ء’¥‡B‚ب‚ا‚ًŒ`ژ®“I‚ة‚àژہژ؟“I‚ة‚àگ³‹Kژذˆُ‚ئ‚ج‘ٹˆل“_‚ھ‘¶چف‚·‚ê‚خپAچ·•ت“Iژوˆµ‚¢‚ة‚ ‚½‚邱‚ئ‚ح‚ب‚¢‚ئچl‚¦‚ـ‚·پB |
|
|
|
 |
”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج“ء’¥‡Bپ@Œظ—p•غڈلVS‚S‚آ‚ج•د“®‘•’uپy“WٹJک_پz |
| ”ٌگ³‹Kژذˆُ‚حŒظ—p•غڈل‚ھژم‚¢‚½‚كپAٹé‹ئ‚ح”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ة‘خ‚µ‚ؤڈم‹L‚ج‚S‚آ‚ج•د“®‘•’u‚ً‹@”\‚³‚¹‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB‚S‚آ‚ج•د“®‘•’u‚حŒظ—p•غڈل‚جŒ©•ش‚è‚ةٹé‹ئ‚ة”ُ‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‹@”\‚إ‚ ‚é‚ج‚إپAŒظ—p•غڈل‚ھژم‚¢”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ة‹@”\‚µ‚ـ‚¹‚ٌپB | |
|
|
 |
”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ج“ء’¥‡Cپ@Œظژ~‚ك‚ة‘خ‚·‚é‰ًŒظŒ —”—p–@—‚ج—قگ„“K—pپyڈoŒûک_پz |
| Œ_–ٌ‚جٹْٹش‚ج’è‚ك‚ھ‚ ‚ê‚خپAٹْٹش–’ھ‚ئ‚ئ‚à‚ةŒ_–ٌ‚ھڈI—¹‚·‚é‚ج‚ھ‘هŒ´‘¥‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA–@—¥ڈم‚إ‚ ‚ê‚خپAŒ_–ٌٹْٹش‚ج’è‚ك‚ھ‚ب‚¯‚ê‚خپAŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚آ‚إ‚àŒ_–ٌ‚ً‰ًڈء‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«پAŒ_–ٌٹْٹش‚ج’è‚ك‚ھ‚ ‚ê‚خپA‚»‚جŒ_–ٌٹْٹش’†‚حŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤ‰ًڈء‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپAگg•ھ•غڈل‚ج–ت‚©‚ç‚¢‚¦‚خپAŒ_–ٌ‚ج–@—ک_‚ً‘O’ٌ‚ئ‚·‚éŒہ‚èپAŒ_–ٌٹْٹش‚ج’è‚ك‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢گ³ژذˆُ‚و‚è‚àŒ_–ٌ‚ج’è‚ك‚ھ‚ ‚éƒtƒ‹ƒ^ƒCƒ}پ[‚ج•û‚ھŒْ‚•غŒى‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB ‚ئ‚±‚ë‚ھپA“ْ–{‚جŒظ—pٹµچs‚إ‚ ‚éڈIگgŒظ—pگ§‚ھپA‘هٹé‹ئ‚ً’†گS‚ئ‚µ‚ؤگ³ژذˆُ‚ة‘خ‚µ‚ؤ’·ٹْŒظ—pŒˆچدƒVƒXƒeƒ€‚ًٹm—§‚µپAچظ”»ڈٹ‚àژg—pژز‚ج‰ًŒظ‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‰ًŒظŒ —”—p‚ج–@—‚ج“K—p‚ً”»—ل‰»‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚و‚èپAژ–ژہڈمپA‰ًŒظ•sژ©—R‚جژہ–±‘جگ§‚ھ‚ئ‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ة‚و‚èپAٹْٹش‚ھ–—¹‚·‚ê‚خŒ_–ٌ‚ھڈI—¹‚·‚é”ٌگ³‹Kژذˆُ‚و‚è‚àپAگ³ژذˆُ‚ج•û‚ھگg•ھ‚ھ•غڈل‚³‚ê‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB گ³ژذˆُ‚ة‘خ‚·‚é’·ٹْŒظ—pŒˆچدƒVƒXƒeƒ€‚جٹm—§‚ة‚و‚èپAŒظ—p‚ج’²گ®•ظ‚ئ‚µ‚ؤŒظ—p‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½”ٌگ³‹Kژذˆُ‚ة‚آ‚¢‚ؤپAŒ_–ٌ“–ڈ‰‚©‚çŒظ—pŒp‘±‚جٹْ‘ز‚ًژ‚½‚¹‚é‚و‚¤‚بŒ¾“®‚ھ‚ب‚¹‚êپAŒ»ژہ‚ةŒظ—pژ葱‚«‚ھ‚¸‚³‚ٌ‚بŒ`‚إŒ_–ٌٹْٹش‚ھ‰½“x‚àچXگV‚³‚ê‚ؤ’·ٹْŒظ—p‰»‚µ‚½ڈêچ‡‚ةپAٹeŒ_–ٌ–—¹‚²‚ئ‚ةŒ_–ٌ‚حڈI—¹‚·‚é‚ئ‚¢‚¤–@‰ًژكڈم‚جŒ´‘¥‚ًٹر‚‚±‚ئ‚ة‹^–â‚ھ‚à‚½‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ج‚و‚¤‚بڈêچ‡‚ةپAŒ_–ٌچXگV‹‘گâ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‰ًŒظŒ —”—p‚ج–@—‚ھ—قگ„“K—p‚³‚êپA‰ًŒظژ葱‚ئ‰ًŒظ——R‚ھ—v‹پ‚³‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤چظ”»—ل‚ھŒ©‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚·پB ‚µ‚©‚µپA‰ًŒظŒ —”—p–@—‚ج—قگ„“K—p‚ح—لٹO“I‚بژو‚舵‚¢‚ئچl‚¦‚é‚ׂ«‚إ‚·پBŒ_–ٌ‚ھچXگV‚³‚ꂽ‚ئ‚µ‚ؤ‚àپAٹeŒ_–ٌٹْٹش‚حٹeپX“ئ—§‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA‚»‚جٹْٹش‚ھ–—¹‚·‚ê‚خپA“–‘R‚ةŒ_–ٌ‚حڈI—¹‚·‚é‚à‚ج‚إ‚·پBŒ_–ٌٹْٹش‚ھچXگV‚³‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤ژ–ژہ‚ھ‚ ‚é‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤپA‰ًŒظŒ —”—p–@—‚ھ—قگ„“K—p‚³‚ê‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB |
|
 |
‰ًŒظŒ —”—p–@—‚ھ—قگ„“K—p‚³‚ê‚éڈê–ت‚ئ‚ح |
| ‰ًŒظŒ —”—p–@—‚ج—قگ„“K—p‚حپA’P‚ةچXگV‰ٌگ”‚ھ‘½‚¢‚ئ‚©پA’تژZٹْٹش‚ھ’·‚¢‚ئ‚¢‚¤ژ–ژہ‚¾‚¯‚إ—قگ„“K—p‚³‚ê‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپBژں‚ج‡@پ`‡E‚جژ–ڈî‚ً‘چچ‡“I‚ةٹ¨ˆؤ‚µپAŒظ—pŒp‘±‚جٹْ‘ز“x‚ج‹“xپA‚»‚جٹْ‘ز‚ھژذ‰ï“I‚ةچ‡—‘¼‰wگ^–ى‚إ–@“I‚ة•غŒى‚·‚é‰؟’l‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚ا‚¤‚©پA‚»‚µ‚ؤ‚»‚ج•غŒى‚ج’ِ“x‚ًچظ”»ڈٹ‚ھ”»’f‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB ڈعچׂحŒْگ¶کJ“ڈب‚جƒٹپ[ƒtƒŒƒbƒg‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB Œْگ¶کJ“ڈبƒٹپ[ƒtƒŒƒbƒg—LٹْکJ“Œ_–ٌ‚ج’÷Œ‹پAچXگV‹y‚رŒظژ~‚ك‚ةٹض‚·‚éٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤ |
|
| ‡@Œ_–ٌ‚ج‹qٹد“I“à—e ‡AŒ_–ٌڈم‚ج’nˆت‚جگ«ٹi ‡B“–ژ–ژز‚جژهٹد“I‘ش—l ‡CچXگV‚جژ葱پEژہ‘ش ‡D‘¼‚جکJ“ژز‚جچXگVڈَ‹µ ‡E‚»‚ج‘¼ |
|
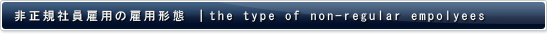
 |
ƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پ[پi’ZژٹشکJ“ژزپj‚ئ‚ح |
| ƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پ[‚ئ‚ح’ZژٹشکJ“ژز‚ج‚±‚ئ‚ً‚¢‚¢پAƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ€کJ“–@‘و‚Qڈً‚إ‚حپu‚PڈTٹش‚جڈٹ’èکJ“ژٹش‚ھ“¯ˆê‚جژ–‹ئڈٹ‚ةŒظ—p‚³‚ê‚é’تڈي‚جکJ“ژز‚ج‚PڈTٹش‚جڈٹ’èکJ“ژٹش‚ة”ن‚µ’Z‚¢کJ“ژزپv‚ئ’è‹`‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAŒْگ¶کJ“ڈب‚ج–ˆŒژ‹خکJ“Œv‚ب‚ا‚ة‚¨‚¯‚éƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پ[‚ج’è‹`‚àپu‚P“ْ‚جڈٹ’èکJ“ژٹشپA‚ـ‚½‚ح‚PڈTٹش‚جڈٹ’èکJ““ْگ”‚ھ“–ٹYژ–‹ئڈê‚جˆê”تکJ“ژز‚و‚è‚à’Z‚¢کJ“ژزپv‚ئ‚µ‚ؤپAکJ“ژٹش‚ج’·’Z‚ة’…–ع‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA‘چ–±ڈبکJ“‹ا‚جکJ“’²چ¸‚إ‚حپAƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پ[‚جˆس–،‚ة‚آ‚¢‚ؤپAپuڈTٹشڈA‹ئژٹش‚ھ‚R‚Tژٹش–¢–‚جکJ“ژزپv‚ئ’è‹`‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB | |
 |
’è”NŒمچؤŒظ—pژزپiڈْ‘ُپj‚ئ‚ح |
| ’è”NŒمچؤŒظ—pژز‚ئ‚حپA‚U‚Tچخ–¢–’è”Nگ§پi—ل‚¦‚خ‚U‚Oچخ’è”Nگ§پj‚ًگف‚¯‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚ة‚¨‚¢‚ؤپAچ‚”N—îŒظ—pˆہ’è–@‘و‚Xڈً‚ة‚و‚茴‘¥‚U‚Tچخ‚ـ‚إ‚جŒظ—pٹm•غ‘[’u‚ھ‹`–±•t‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپA‚±‚ê‚ةڈ]‚¢’è”N‘قگE‚µ‚½Œم‚ةچؤŒظ—p‚µ‚½کJ“ژز‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پBٹَ–]ژز‘Sˆُژل‚µ‚‚حˆê’èٹîڈ€‚ً–‚½‚µ‚½کJ“ژز‚ًچؤŒظ—p‚µ‚ـ‚·پBˆê”ت“I‚ةپAٹْٹش‚ج’è‚ك‚ج‚ ‚éکJ“Œ_–ٌ‚إ‚ ‚èپAڈْ‘ُ‚ئŒؤ‚خ‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢پB | |
 |
ƒAƒ‹ƒoƒCƒgپAƒtƒٹپ[ƒ^پ[‚ئ‚ح |
| ƒAƒ‹ƒoƒCƒg‚ئ‚حپAˆê”ت“I‚ةپu‘¼‚ة–{‹ئ‚ھ‚ ‚è‚ب‚ھ‚çپAگ¶ٹˆ‚ج•›ژû“ü‚ً“¾‚é–ع“I‚إڈAکJ‚µ‚ؤ‚¢‚éکJ“ژزپv‚ً‚¢‚¢‚ـ‚·پB—ل‚¦‚خپA–{‹ئ‚ھٹw‹ئ‚إ‚ ‚è‚ب‚ھ‚炨ڈ¬Œ‚¢‚ً“¾‚邽‚ك‚ةڈAکJ‚·‚éٹwگ¶‚ب‚ا‚ھ‘م•\“I‚إ‚·پBٹwگ¶ƒAƒ‹ƒoƒCƒg‚حپAٹwچZ‚ً‘²‹ئ‚·‚é‚ـ‚إ‚جڈAکJ‚ھ‘O’ٌ‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA‘²‹ئŒم‚à’èگE‚ةڈA‚©‚¸پAٹwگ¶ژ‘م‚ئ“¯—l‚جƒAƒ‹ƒoƒCƒg“I‚بڈAکJ‚ً‘±‚¯‚éکJ“ژز‚ًƒtƒٹپ[ƒ^پ[‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·پBƒtƒٹپ[ƒ^پ[‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAکJ“—ح’²چ¸‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚é‘چ–±ڈب‚حپA”N—î‚P‚Tچخپ`‚R‚Sچخ‚إپA’jگ«‚ح‘²‹ئژزپAڈ—گ«‚ح‘²‹ئژز‚إ–¢چ¥‚جژز‚ئ‚µپA‡@Œ»چفڈA‹ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éژز‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‹خ‚كگو‚ة‚¨‚¯‚éŒؤڈج‚ھپuƒpپ[ƒgپv‚ـ‚½‚حپuƒAƒ‹ƒoƒCƒgپv‚إ‚ ‚éژز‡AŒ»چف–³‹ئ‚جژز‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‰ئژ–‚à’تٹw‚à‚µ‚ؤ‚¨‚炸پuƒpپ[ƒgپEƒAƒ‹ƒoƒCƒgپv‚جژdژ–‚ًٹَ–]‚·‚éژز‚ئ’è‹`‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBŒْگ¶کJ“”’ڈ‘‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚à“¯—l‚ة’è‹`‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB | |
 |
ٹOچ‘گlکJ“ژز‚ئ‚ح |
| ٹOچ‘گl‚ھ“ْ–{‚ة“üچ‘‚µچف—¯‚·‚邽‚ك‚ة‚حپA“üچ‘گRچ¸ٹ¯‚ةڈم—¤گ\گ؟‚ً‚µپAگRچ¸‚ًژَ‚¯‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپi“üٹا–@‘و‚Uڈً‚Qچ€پjپB‚»‚µ‚ؤپA“üچ‘ٹا—ٹ¯‚حپA—·Œ”پiƒpƒXƒ|پ[ƒgپj‚âچ¸ڈطپiƒrƒUپj‚ھ—LŒّ‚إ‚ ‚é‚©پAچف—¯ژ‘ٹi‚جٹîڈ€‚ة“Kچ‡‚·‚é‚©‚ًگRچ¸‚µ‚½‚¤‚¦‚إپAڈم—¤‹–‰آپiچف—¯‹–‰آپj‚ًڈo‚µ‚ـ‚·پi“üٹا–@‘و‚Vڈً‚Pچ€پA‘و‚Xڈً‚Pچ€پjپBٹOچ‘گlکJ“ژز‚ھ“ْ–{چ‘“à‚إڈAکJ‚·‚邽‚ك‚ة‚حڈAکJ‰آ”\‚بچف—¯ژ‘ٹiپiپuٹˆ“®‚ةٹî‚أ‚چف—¯ژ‘ٹiپvپj‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ•K—v‚إ‚·پB“üٹا–@‚إ‚حپAچ‚“x‚ب‹Zڈp‚âگê–هگ«‚ً‚à‚ء‚½ٹOچ‘گl‚ة‚ج‚فڈAکJ‰آ”\‚بچف—¯ژ‘ٹi‚ً•t—^‚·‚邱‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA’PڈƒکJ–±چى‹ئ‚ةڈ]ژ–‚·‚éٹOچ‘گlکJ“ژز‚حژَ‚¯“ü‚ê‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚½‚¾‚µپAپu‰iڈZژزپv‚âپu’èڈZژزپv‚ب‚ا‚جپuگg•ھ‚ـ‚½‚ح’nˆت‚ةٹî‚أ‚چف—¯ژ‘ٹiپv‚ھ•t—^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éٹOچ‘گl‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAٹˆ“®‚ةگ§Œہ‚ھ‚ب‚پA’PڈƒکJ–±چى‹ئ‚ًٹـ‚ك‚ؤ“ْ–{چ‘“à‚إ‚جڈAکJ‚ھ‰آ”\‚إ‚·پB‚ـ‚½پAژ‘ٹiٹOٹˆ“®‚ج‹–‰آ‚ً‚à‚炤‚±‚ئ‚إˆê’èژٹشگ”‚جƒAƒ‹ƒoƒCƒg‚ھ‹–‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éٹOچ‘گl—¯ٹwگ¶‚âڈAٹwگ¶‚à’PڈƒکJ–±چى‹ئ‚جڈAکJ‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB | |

| ٹé‹ئ‚ھکJ“—ح‚ً—ک—p‚·‚éŒ`‘ش‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAکJ“ژز‚ئ’¼گعŒ_–ٌ‚ً‚µ’¼گع—ک—p‚·‚éŒ`‘ش‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚پA‘¼ٹé‹ئپi‘¼گlپj‚ھŒظ—p‚·‚éکJ“ژز‚ًپA“–ٹY‘¼ٹé‹ئ‚ئ‚جŒ_–ٌ‚ً‰î‚µ‚ؤٹشگع—ک—p‚·‚é•û–@‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB |
|
|
 |
کJ“ژز”hŒ |
| کJ“ژز”hŒ‚ئ‚حپAپuژ©Œب‚جŒظ—p‚·‚éکJ“ژز‚ًپAژ©Œب‚ئ‚جŒظ—pٹضŒW‚ج‰؛‚ةپA‚©‚آپA‘¼گl‚جژwٹِ–½—ك‚ًژَ‚¯‚ؤپA“–ٹY‘¼گl‚ج‚½‚ك‚ةکJ“‚ةڈ]ژ–‚³‚¹‚邱‚ئ‚ً‚¢‚¢پA“–ٹY‘¼گl‚ة‘خ‚µ‚ؤ“–ٹYکJ“ژز‚ً“–ٹY‘¼گl‚ةŒظ—p‚³‚¹‚邱‚ئ‚ً–ٌ‚µ‚ؤ‚·‚é‚à‚ج‚ًٹـ‚ـ‚ب‚¢پv‚ئ’è‹`‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پi”hŒ–@‘و2ڈً1چ†پjپBŒم”¼•ھ‚جپu“–ٹY‘¼گl‚ة‘خ‚µ‚ؤ“–ٹYکJ“ژز‚ً“–ٹY‘¼گl‚ةŒظ—p‚³‚¹‚邱‚ئ‚ً–ٌ‚µ‚ؤ‚·‚é‚à‚جپv‚ئ‚حچفگذڈoŒü‚ج‚±‚ئ‚ًژw‚µپAچفگذڈoŒü‚حکJ“ژز”hŒ‚ة‚©‚çڈœ‚‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إ‚·پB کJ“ژز”hŒ‚حپuŒظ—pپv‚ئپuژg—pپv‚ھ•ھ—£‚µ‚½Œظ—pŒ`‘ش‚إ‚ ‚éپA‚ئ•\Œ»‚³‚ê‚ـ‚·پB کJ“ژز”hŒ‚ًچs‚¤‚ة‚حپAچsگ‚ج‹–‰آپiˆê”تکJ“ژز”hŒپj‚âچsگپi“ء’èکJ“ژز”hŒپj‚ض‚ج“حڈo‚ھ•K—v‚إ‚·پB‹–‰آ‚â“حڈo‚ب‚کJ“ژز”hŒ‚ًچs‚¤‚ئپA‚»‚ê‚حگE‹ئˆہ’è–@‘و44ڈً‚إ‹ضژ~‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éکJ“ژز‹ں‹‹‚ةٹY“–‚µ”±‘¥‚ھ“K—p‚³‚ê‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپAکJ“ژز”hŒ–@ڈم‚ج”±‘¥‚ح”hŒŒ³‚ة‚µ‚©“K—p‚³‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAگE‹ئˆہ’è–@ڈم‚ج”±‘¥‚ح‹ں‹‹Œ³‚¾‚¯‚إ‚ب‚‹ں‹‹گو‚ة‚à“K—p‚³‚ê‚ـ‚·پB‹t‚جژ‹“_‚إ‚ف‚ê‚خپAگE‹ئˆہ’è–@‚إ‹ضژ~‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éکJ“ژز‹ں‹‹‚ًچ‡–@“I‚ة—ک—p‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚½‚à‚ج‚ھکJ“ژز”hŒ‚ئ‚¢‚¤کJ“—ح—ک—p‚ة‚ب‚é‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB |
|
|
|
|
 |
گ؟•‰ |
| گ؟•‰‚ئ‚حپAژè’i‚ئ‚µ‚ؤ‚جکJ“—ح‚إ‚ح‚ب‚پAکJ“‚جŒ‹‰ت‚إ‚ ‚éژdژ–‚جٹ®گ¬‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚ـ‚·پi–¯–@‘و632ڈًپjپB‚½‚ئ‚¦‚خپA‚ ‚é•”•i‚جگ»‘¢‚ًگ؟•‰ٹé‹ئ‚ة”’چ‚µ‚½‚ئ‚·‚é‚ئپA”’چٹé‹ئپi’چ•¶ژهپj‚حگ؟•‰ٹé‹ئ‚إگ»‘¢‚³‚ꂽ•”•i‚جٹ®گ¬‚ً‘ز‚؟پA‚»‚جŒ‹‰ت‚ة‘خ‚µ‚ؤ•ٌڈV‚ًژx•¥‚¤‚±‚ئ‚ئ‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB‚آ‚ـ‚èپAگ؟•‰‚إ‚حپA”hŒ‚ئˆظ‚ب‚èپA’چ•¶ژه‚ھ’¼گعگ؟•‰ٹé‹ئ‚جکJ“ژز‚ةژwٹِ–½—ك‚·‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤“_‚ة‘ه‚«‚ب“ء’¥‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB ‚½‚¾‚µپA”hŒ‚ئ‚ج‹و•ھٹT”O‚إ—p‚¢‚ç‚ê‚éگ؟•‰‚ة‚حپAژdژ–‚جٹ®گ¬‚ً–ع“I‚ئ‚·‚é–¯–@ڈم‚جگ؟•‰‚ةŒہ‚炸پAژ––±پi‹ئ–±پjڈˆ—‚ب‚ا‚جˆد”CپEڈ€ˆد”C‚àٹـ‚ـ‚ê‚ـ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خپA•K‚¸‚µ‚àژdژ–‚جٹ®گ¬‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚ب‚¢ƒrƒ‹‚جٹا—‚âگ´‘|پAژَ•t‹ئ–±‚ئ‚¢‚ء‚½’P‚ب‚éژ––±پi‹ئ–±پjڈˆ—‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAگ؟•‰ٹé‹ئ‚ھ“–ٹY‹ئ–±‚ًژَ‘ُ‚µپA“ئ—§‚µ‚ؤڈˆ—‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپA”hŒ‚ئ‚ج‹و•ت‚جٹضŒW‚إ‚ح‰EŒX‚¨‚¢‚ؤ‚µ‚ؤ’è‹`‚أ‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |
|
|
|
|